文学通信Bungaku Report
公式サイト: https://bungaku-report.com/
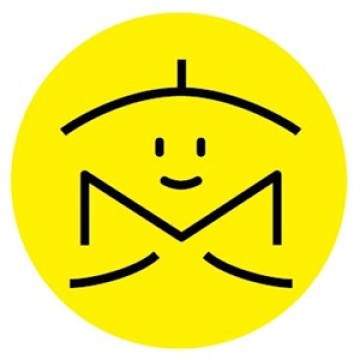
日本語・日本文学の研究書を中心に、人文学書全般を刊行する出版社。文学だけにこだわらず周辺領域も含め、意欲的に刊行していきます。出版活動と同様に、webでも積極的に活動することで、多様な情報をつなげ、多くの「問い」を世に生み出していきたいと思います。もっと読む


アマビエ、クダン、姫魚……ユルく、愛らしく、謎な獣たち!予言獣はこんなにいた!150点以上の資料を収めた、長野栄俊編・岩間理紀・笹方政紀・峰守ひ…


江戸から明治の転換期を生きた、松廼家露八(まつのやろはち)こと土肥庄次郎。彰義隊として戦い、そののち幇間に転身した彼はなにを思い、生きたの…


歴史のかなたにある遠いもの…と感じられがちな江戸の和本(わほん)。そんな和本の世界を、200点超の写真・図版で魅せるグラフ誌『和本図譜 江戸を究…


新宿・大久保駅周辺は、明治から大正にかけて多くの文学者、ジャーナリスト、社会主義者が住み、牛が寝そべる牧場がある、のどかな郊外の文士村だっ…


学校で誰しもが学習する「矛盾」「完璧」「塞翁が馬」などの故事成語。これらは中国の歴史故事を背景として生まれ、その一部は日本で独自の変容を遂…


18世紀から19世紀の日本には、絵と文字(くずし字)を組み合わせて見開き2ページで一画面を構成し、一つの物語を展開するという形式の草双紙(くさぞ…


不知火海(しらぬいかい)とともに生きた詩人・作家、石牟礼道子(1927~2018)。『苦海浄土』をはじめとする彼女の作品に、浄瑠璃、説経節、近代以…


土偶は「植物」の姿をかたどった精霊像という説を打ち出した『土偶を読む』(晶文社)を検証する書籍『土偶を読むを読む』(文学通信)が刊行されま…


近年、さまざまな分野において、古文書を「モノ」として捉えて観察する研究手法への関心が高まってきています。古文書研究の新たな可能性にせまるガ…


漢字語彙の多義性を利用し、違う意味に読み替えていく、または、本来の語彙・文字を分解・変形させるなど、多様な技巧が含まれる、燈謎(とうめい)…


学芸員というお仕事の悲喜こもごもを描き、SNSでも人気を博した四コマまんが『学芸員の観察日記 ミュージアムのうらがわ』がこのたび書籍化されまし…


関ヶ原の合戦や江戸幕府を開いた人物として日本の歴史にその名を刻む、徳川家康。2023年のNHK大河ドラマの中心人物である家康だが、その幼き日々から…


日本のみならず、世界でも大きく注目される川瀬巴水(かわせはすい)。明治・大正・昭和の日本全国を旅し、誰も注目しないような無名で当たり前の風…


東日本大震災後、福島出身の雑誌『日本古書通信』編集者が見続けてきた東北の古本屋の記録をまとめた『増補新版 東北の古本屋』(文学通信)が10月に…


「なぜ古典を学ばなければならないのか」という生徒たちの声に、どう応えればいいのか。古典教育に対する議論を成立させるには、まずどのような前提…


「神話」といえばいにしえの神々の物語か、国家共同体の起源を明らかにする、時間も場所も遠く遠く隔たった世界の話というイメージがいまでも根強い…


俳句を深く理解し、詠む・読むためにはどうすればいいのか。「ルール」にがんじがらめにされずに、俳句をもっと楽しむにはどうすればいいのか。俳句…


『文学授業のカンドコロ 迷える国語教師たちの物語』(文学通信)は、学校現場の先生たちに、文学授業を行ううえでの基礎理論をわかりやすく伝える本…


卒論を書くと、学生と大学にとってどういうイイことがあるのか?卒論は学生と大学双方にとって相当面倒なものにしか思えない。なぜ、こんな大変なも…


2020年8月末、東京都練馬区にあった遊園地が多くの人々に惜しまれながら閉園した。大正時代より94年間続いた「としまえん」。世界初の流れるプールに…