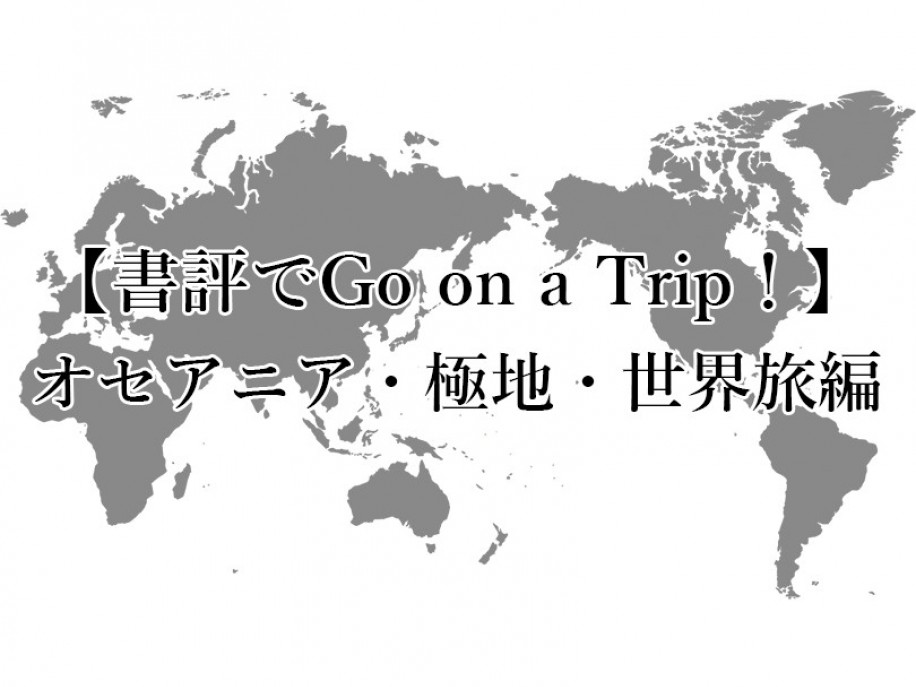読書日記
夏休み企画(書評でGo on a Trip ! )西欧編

世界各地を〈書評〉で巡る〈書評でGo on a Trip!〉企画、西欧編です!
西欧にGo!
【イギリス】
■カズオ・イシグロ『忘れられた巨人』(早川書房)
評者:豊崎 由美アクロバティックな語りによってカズオ・イシグロが伝えようとしているのは、国家レベルの忘却が生むかもしれない今・此処の危機なのである。(この書評を読む)
【イギリス】
■ブレイディ みかこ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)
評者:永江 朗イギリスがEUを離脱するきっかけは移民問題だった。ブレイディみかこの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』を、多様化と差別と子どもという観点で読むといろいろ勉強になる。著者はいまもっとも注目されるライターで、イギリスの現在を労働者の街から伝える。(この書評を読む)
【イギリス】
■アーヴィン・ウェルシュ『トレインスポッティング』(早川書房)
評者:杉江 松恋イギリスの文化は、正統=イングランド・国教会と異端=イングランド以外のイギリス・カソリックとの対立で成立している。ポップに浮遊するかに見えるウェルシュの小説も、彼がスコットランド人であるという出自ゆえに、この対立構造の上に立脚した小説なのである。(この書評を読む)
【イギリス】
■イヴ・K・セジウィック『男同士の絆―イギリス文学とホモソーシャルな欲望―』(名古屋大学出版会)
評者:大橋 洋一シェイクスピアからディケンズにいたる英文学史上の古典を題材にした緻密な議論を展開しながら、「ホモソーシャル」概念を、わたしたちにとって使用可能にしてくれるまさに待望の翻訳である。それは「ホモソーシャル」の意味と、その驚くべき適用可能性をいかんなく示してくれる。(この書評を読む)
【イギリス】
■中島 俊郎『イギリス的風景―教養の旅から感性の旅へ』(NTT出版)
評者:高山 宏独自の風景観を持たなかった18世紀初頭の英国紳士たちはイタリアを美の理想の標的に決め、イタリア風景を絵の形で輸入し、それを英国という異土で立体的に立ち上げるという倒錯を演じた。英国華紳の教養の印がイタリア風景にどれほど通じているかで測られた。歩きながら、これは画家某が描いたイタリアのどこそこの風景と見抜いていくのが、教養の印。(この書評を読む)
【アイルランド】
■ウィリアム・トレヴァー『聖母の贈り物』(国書刊行会)
評者:豊崎 由美トレヴァーの人間を見つめる視線には容赦がありません。けれど、絶望を絶望として描きながらも、その眼差しの奥には、残酷な宿命を受け入れるしかない人間の諸相を肯定する励ましという光が見えるように、わたしには思えるのです。(この書評を読む)
【アイルランド】
■『ユリシーズ航海記: 『ユリシーズ』を読むための本』(河出書房新社)
評者:池内 紀世界の文学のなかで、とびきり翻訳が厄介な作品が二つある。一つはジョイスの『ユリシーズ』であり、もう一つはジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』である。(この書評を読む)
【フランス】
■堀江 敏幸『河岸忘日抄』(新潮社)
評者:豊崎 由美無人島に持っていける本を一冊選べと言われたら、今のわたしなら間違いなくこの小説を選びます。物語と思惟(しい)と語りがこれほど清冽な流れをなしている作品は、それほど多くはないのですから。(この書評を読む)
【フランス】
■野崎 歓『フランス小説の扉』(白水社)
評者:堀江 敏幸ふたつの世紀にまたがる芸術を、これほどやわらかい紐で結んでくれた事例はかつてなかったし、とりわけ「今なお興奮を味わわせてくれる傑作の数々が、断固『反フランス的』なものとして書かれている」との指摘は、けだし名言と言って差しつかえないだろう。その名言を支えているのが、あちこちで輝きを放つ、鋭い批評の数々だ。(この書評を読む)
【フランス】
■ル・クレジオ『ル・クレジオ、映画を語る』(河出書房新社)
評者:野崎 歓それにしても、ノーベル賞作家がなぜここまで映画に惚れ込み、夢中になって語るのか。スクリーンという「鏡」は、他者への共感を促すとともに観客自身をも映し出す。「自分が何者なのか」を教えてくれる点にも映画の「呪術」としての魅惑がある。(この書評を読む)
【フランス】
■ミシェル・ウエルベック『服従』(河出書房新社)
評者:柳下 毅一郎ウエルベックは問いかける。人は自由を求めてきた。自由を求めて王を殺し、神を殺した。だが、本当にそれで現代人は幸福になったのだろうか? この小説が本当に恐ろしいのは、その答えが説得力をもって迫ってくるところである。(この書評を読む)
【フランス】
■パリ憧憬の文学九選
評者:鹿島 茂バルザックの小説は、いかに生くべきかを追い求める、旧制高校的な読書とはおよそ無縁である。というよりも、たいていは、成り上がることばかりを考えている俗物的な青年が主人公になっている。『ゴリオ爺さん』の場合も主人公はパリに上り、立身出世を望むラスチニャックという学生である。(この書評を読む)
【ベルギー】
■I・プリゴジン『混沌からの秩序』(みすず書房)
評者:吉本 隆明「今日の知見によれば、生物圏は全体としてもその個別成分としても、それが生きていようが死んでいようが、平衡から遠く離れた状態にある。この文脈から、生命は自然の秩序から遠く離れて、実際に起った自己組織化過程の最高の形態のようにおもえる」 (この書評を読む)
【ベルギー】
■ルイズ・ド・ラ・ラメー『フランダースの犬』(徳間書店)
評者:森 まゆみ幼稚園の紙芝居によると、絵を見た喜びに満足したネロとパトラッシは疲れてすやすやと眠り、翌朝、目覚めてまた元気に木の車を引っぱって、村に帰るはずであった。たしかそうなっていた。(この書評を読む)
【スイス】
■フリードリヒ・デュレンマット『失脚/巫女の死 デュレンマット傑作選』(光文社)
評者:鹿島 茂デュレンマットの作品というのは現代の「寓話(ぐうわ)」で、読者は常に自分が生きている時代の「なにか」を連想させられることになる。(この書評を読む)
【スイス】
■宮下 誠『越境する天使 パウル・クレー』(谷川 渥)
評者:谷川 渥「クレーは、これまで一般に考えられてきたような、天使のようなイノセントな画家でもナイーヴな画家でも金輪際、ない」と氏は書いている。(この書評を読む)
【ドイツ】
■トーマス・マン『魔の山』(新潮社)
評者:辻井 喬人間に対する感性的な認識がおろそかにされないのなら、小説という芸術の形式が世界を相手にしてこのような虚構を描き得るのだという発見は私の心を震撼しつづけた。(この書評を読む)
【ドイツ】
■ベルンハルト・シュリンク『夏の嘘』(新潮社)
評者:池内 紀ちょっとした嘘、とっさに、あるいは何げなく口にした嘘、わざと言わずにおいた無言の嘘。みずから封印していた嘘と対面して、男と女の日常が微妙にもつれ、変化していく。気がつくと、「一緒の生活はもう終わるが、元の自分の生活にもまだ戻ってはいない。無人地帯にいるようなものだった」。(この書評を読む)
【ドイツ】
■W・G・ゼーバルト『アウステルリッツ』(白水社)
訳者あとがきアントワープ、ロンドン、プラハ、テレージエンシュタット、マリーエンバート、ニュルンベルク、パリ……いわれのない衝動に駆られるまま、あるいは抑圧してきた過去を取り戻すべく彼が訪れるヨーロッパの諸都市。それは個人と歴史の深みへと降りていく旅だった。(この書評を読む)
【オーストリア】
■クラウディオ・マグリス『オーストリア文学とハプスブルク神話』(書肆風の薔薇)
評者:種村 季弘ハプスブルク家を帝統として維持された帝国はほぼ千年続き、一九一八年に消滅した。では、多民族多言語国家としてたえず民族主義的分離主義による解体の危機に脅かされながら、ヨーロッパ千年の激動の歴史のなかでこの国がなぜ安定を保っていられたのか。マグリスは、その秘密を「ハプスブルク神話」にさぐる。(この書評を読む)
【オーストリア】
■トーマス・ベルンハルト『破滅者』(みすず書房)
評者:山崎 正和ベルンハルトの小説集『破滅者』は、二編の中編作品、表題作と「ヴィトゲンシュタインの甥」からなっているが、いずれも要約すればこの「わかる」人の「わかる」がゆえの悲劇だといえる。二作とも主人公がわかるのは音楽だが、尋常ならぬわかり方が彼らを狂わせ、ついには自殺へと導いてゆく。(この書評を読む)
【オーストリア】
■ペーター・ハントケ『幸せではないが、もういい』(同学社)
評者:豊崎 由美勉強することは許されず、愛する男とは結婚できず、夫と子供たちの世話をするだけの齢を重ねていくかつてはざらに見られた女たちの一人だった母。ハントケはその凡庸ではあっても、本人にとっては比類なき人生を、ナチスの軍靴に踏みにじられたヨーロッパの歴史に重ね合わせようと試みる。が、それはよく出来た“お話”のようにうまくは運ばない。(この書評を読む)
【オランダ】
■アンソニー・ベイリー『フェルメール デルフトの眺望』(白水社)
評者:高階 秀爾アンソニー・ベイリーの『フェルメール デルフトの眺望』は、当時の社会状況に広く眼配りすることによって資料の不足を補いながら、この謎の画家の本質に迫ろうとした労作である。例えば、彼が師事した、あるいは影響を受けた可能性のある画家が数多く紹介されている。(この書評を読む)
ALL REVIEWSをフォローする